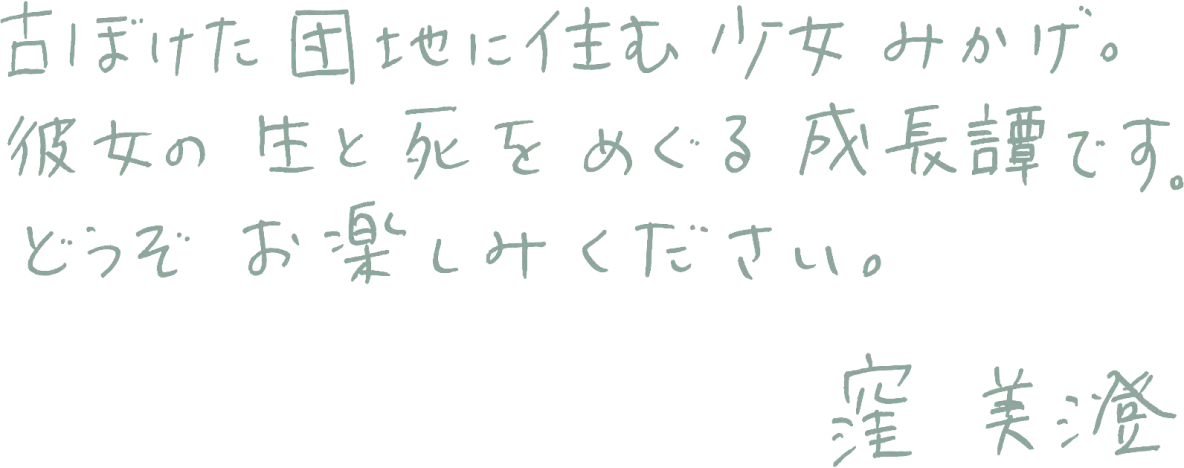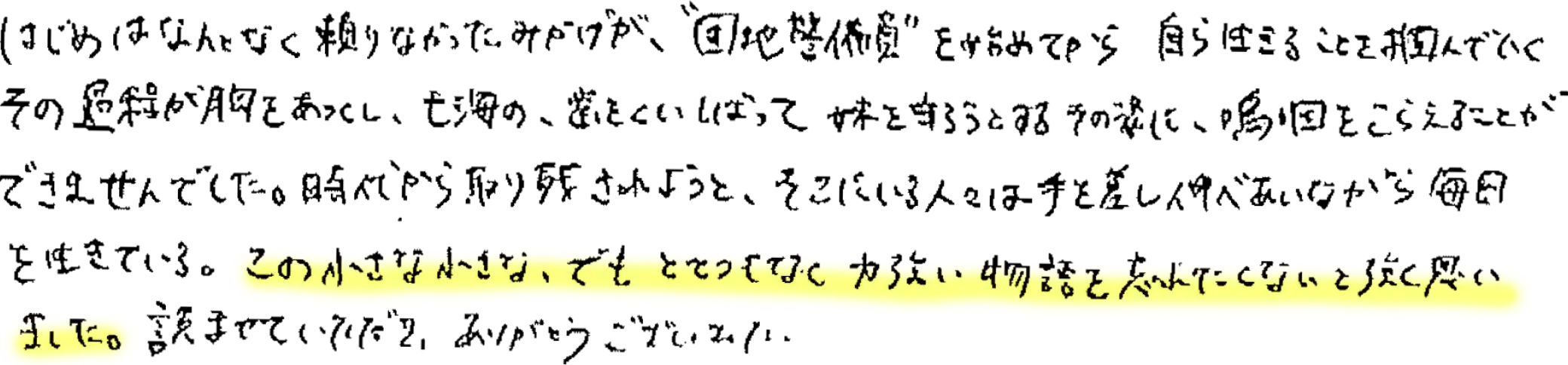
装画=宮崎夏次系


あらすじ


お知らせ
雑誌
2023.2.3
WEB
2023.1.23
少女の世界はあまりに脆く、簡単に崩れ去る
WEB
2023.1.17
雑誌
2023.1.6
WEB
2022.12.19
release
2022.12.14
薄暗い場所の終わり、軽やかな生の始まり
「本物の死体には、色も質感も臭いもある。そしてそれは、団地全体に常に漂っている臭いと言ってもいいだろう。そこには生きることのしんどさが詰め込まれている。」
書評坂上秋成(作家)
ここには「ほどほどの弱者」が描かれている。
十五歳の少女、みかげは姉である七海と二人で暮らしている。彼らが住んでいるのは森に囲まれた築五十年を超える団地で、そこはスラムと称され、自殺の名所としても有名になっている。団地の治安の悪さ、住人たちの貧困さ、状態が不安な独居老人の多さといった薄暗い要素が描写の端々から伝わってくる。
みかげは頭がいささか「とろい」上に喘息もちで身体も弱いため、昼の学校でいじめに遭い、現在はパン工場でアルバイトをしながら夜間の高校に通っている。
ある日、彼女はぜんじろうという老人に誘われる形で、団地警備員の仕事を手伝うことになる。生き残っている人間の生存確認、子どもたちの安否確認、それから、飛び降り自殺をしようとしている人間がいないかどうかの確認。これらが団地警備員の仕事だ。もともと人間の死体を見たいと考えていたみかげは、この手伝いをしていれば飛び降りの死体に出会えるのではないかと期待する。
肉体や知能に多少の問題があろうとも、みかげの生活は楽しそうなものに映る。彼女には倉梯くんとむーちゃんという二人の友人がいる。倉梯くんは吃音症を、むーちゃんは在日コリアンであることを理由にそれぞれいじめを受けた過去を持ち、みかげと同じ高校に通っている。やがて二人は団地警備員に加わることになるが、その様子はさながら、年相応の子どもたちが本来あり得た青春として部活動を行うかのようだ。
だが、おだやかな筆致でありつつも、本作における楽しさや幸福は常にあやうさをまとっている。
そのあやうさは、メインの舞台である団地に強く紐づいている。そこは孤独死や自殺がいつ起きても不思議のない場所であり、みかげは実際に、知り合いの男児の母親が死んでいる様を目撃する。だが死体は決して、彼女が夢見ていたようなものではなかった。本物の死体には、色も質感も臭いもある。そしてそれは、団地全体に常に漂っている臭いと言ってもいいだろう。そこには生きることのしんどさが詰め込まれている。
たとえば、姉の七海が置かれている状況にしてもそうだ。彼女は生活費を稼ぎながら貯金をし、やがては美容師になりたいと考えているが、そのための手段として選択した職業はデリヘルであり、しかも仕事内容に疲弊している。彼女の疲労や仕事の危険性を感じ取るがゆえに、みかげは七海がデリヘルを続けることに反対する。仕事を続けることで、七海がしんどさに飲みこまれることをみかげは理解しているのだ。
団地とそこに生きる人間たちは社会システムの外に置かれている。しかし、それは社会問題化するほどに決定的な外部ではない。ほどほどに貧しく、ほどほどに孤独で、ほどほどに疲れている。そうした「ほどほどの弱者」に対して、行政は、あるいは社会は、救済として入りこめない。
だからこそ、みかげやぜんじろうの団地警備は重要な意味を持つ。本作の後半では団地の取り壊しに反対する形で、高校生による反対運動が起きるものの、それは非常に薄い思想に映るし、あっという間に大人たちの運動へと姿を変えてしまう。
翻って、団地警備員の活動はどうか。それぞれのメンバーが、一軒一軒部屋をおとずれ、話しかけ、飲み物や食べ物を提供する。社会システムが助けてくれない人間の不安や孤独に対して手を差し伸べる。それはきわめてささやかな行為でありながら、大上段に構えたナタを振るうよりもはるかに尊い行為と映る。
ぜんじろうが始めた団地警備員の仕事は、最終的に三人の子どもたちへ受け継がれていく。団地がなくなってしまう以上、活動そのものが残るわけではない。だがラストシーンにおいて、子どもたちは活動の中で自身が変化したことを感じ、それに伴う形で未来を思い描く。
その時彼らは、ほどほどに大人であり、そして同時に、ほどほどに子どもと呼ぶべき軽やかな存在なのだ。
(初出:「ちくま」22年12月号)
#デスバスに寄せられた声
刊行前から書店員さんの熱い感想、届いています
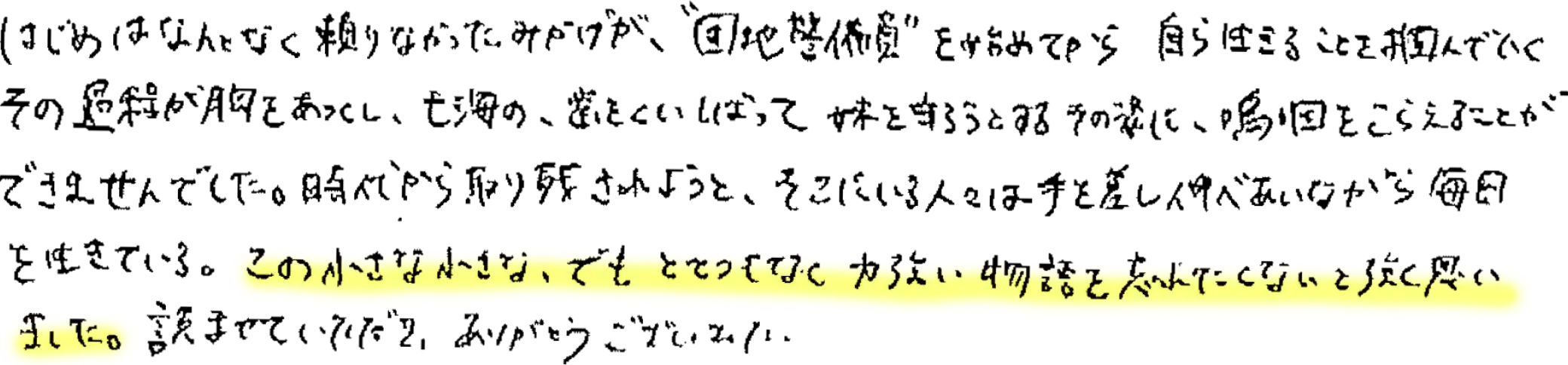

望月美保子さん
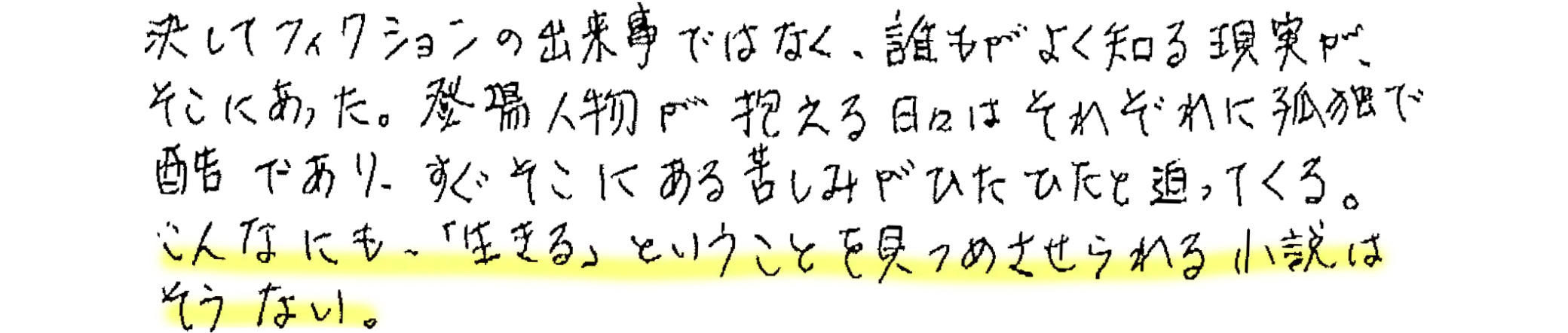
本郷綾子さん
#デスバス
でつながろう。窪 美澄
タイム・オブ・デス、
デート・オブ・バース
明るい未来なんて思い描けない、この場所で
自分だけの生を、未来をつかみ取っていく
希望溢れる長編小説。
装画=宮崎夏次系
定価: 1,540円(10%税込)/ISBN:978-4-480-80509-6