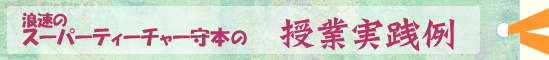|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 前のページへ | 1/2/3/4 | 次のページへ |
③ 「私」を解きほぐす――身体の記憶(私さがし)
「なぜ手榴弾を投げたのか?」というヒミツの答えは、「身体が恐怖を感じたから」ということなのですが、それでは、「身体」は何に恐怖を感じたのでしょうか。これが二つ目のヒミツです。「条件反射で投げてしまった」と答える生徒もいますが、それなら、その「条件」とはどういうものなのでしょうか。それと軍隊の訓練との因果関係が明確であれば、主人公はこれほど苦悩しないでしょう。「身体」が何に反応し、恐怖したのかわからないことで、主人公は自分の中の見知らぬもう一人の自分の存在を感じているのです。しかし、主人公がその答えを導き出すのはそう簡単なことではありません。なぜなら、「身体」が見て感じとっていることについて「私」は疎外されているからです。つまり、主人公が執拗にこのヒミツの答えを追い求めるのは、結局、自分の中にもう一人の見知らぬ自分を探し求めているということでもあるのです。自分で自分がわからなくなったという頼りなさ、自分からの疎外感、自分との不一致感がそこに見て取れます。
この小説の表現の特徴は、出来事を出来る限り客観的に振り返ろうとする姿勢にあります。最初に述べた「私」と「身体」との「体験」の違いもその一つですが、その他にも「私」ともう一人の「私」、「身体」との「体験」の違い、「記憶」の違いを厳密に検証しています。
彼は片手に武器を持っていた。銃口は下に向けられていた。とくに急ぐ様子もなく、彼は道の真ん中を歩いていた。音はまったく聞こえなかった。音を聞いた記憶はまったくない。
手榴弾は一度跳ねて、それから道の上をごろごろと転がった。私にはその音は聞こえなかった。しかし音はしたのに違いない。
「私」には聞こえていない音も、あるいは記憶していない音でも、「身体」には聞こえているに違いありません。「身体」がどのような音を聞き、「身体」に記憶していたのか検証しているのです。「身体」はその音に反応したのかもしれませんから。
そしてその青年はまるで目に見えないワイヤにひっぱられるみたいに、上の方に向かって体をねじった。彼は背中から地面に落ちた。彼のゴムのサンダルは吹き飛ばされた。風はなかった。彼は小道の真ん中に横たわった。彼の右脚は体の下に折り畳まれるように潜りこんでいた。彼の右目は閉じていた。左目は星の形をした大きな穴になっていた。
非常に冷静で客観的な描写です。しかし、「私」の心情には一切触れられていません。ここで問題なのは「私」ではなく「身体」であり、その「身体」には何が見えていたのか、ということが大事なのです。「身体」が見たであろうものを検証しているのです。
自分の中にもう一人の自分がいて、自分の関与できないところで重大事をいつ引き起こすかわからないという不安。もう一人の自分は何を見ていたのか、何に恐怖したのかを探ることは、出口のない迷路のようなものです。「身体」の記憶がいつ始まり、何を記憶し、人を殺すに至ったのか。それはベトナム戦争の惨禍の記憶かもしれません。それ以前の新兵訓練(Recruit training)でたたき込まれたものかもしれません。いやもっと前の生育歴に関係しているかもしれません。わからないからこそ主人公は戦争にこだわり、自分にこだわり続けるのです。それにしても、戦争が普段は見えない人間の本質を露呈させるということはだけは確かなように思えます。
小説の冒頭に、九歳の娘に「お父さんって戦争の話ばかり書いているじゃない。」「だからだれか殺したはずだって思うの。」と聞かれた主人公が、「まさか、殺してなんかいないよ。」と返答する場面があります。なぜ、娘に本当のことを話さなかったのでしょうか。まだ十分に物事の判断ができない子どもに、たとえ戦争であったとしても自分の父親が殺人者あるということを知らせることが得策でないと判断したということもあるでしょうが、そればかりではないように思えます。主人公には、自分の行為が非常時におけるやむを得ぬ行為だと言い切れないからです。それ故、子どもの疑問に誠実に答えようとすれば、自分の中のもう一人の自分のことに言及せざるを得ず、九歳の娘にそれを話しても混乱するばかりだと判断したのでしょう。自分の父親や自分の中にもう一人の自分がいるという人間の心の闇を九歳の子どもに教えるのは確かに早すぎますよね。主人公は、成人した娘に話すつもりでこの話を書いているのです。そしてそれは、自分自身を解きほぐし、失われた自分との一体感や、自分自身を取り戻すための行為でもあるのです。
| 前のページへ | 1/2/3/4 | 次のページへ |
| ● 1 『待ち伏せ』の指導案をダウンロード | 一太郎版 |