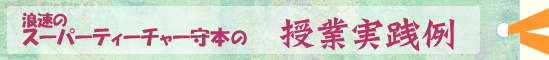|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 前のページへ | 1/2/3 | 次のページへ |
b 柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺 正岡子規
有名な句です。一見すれば何気ないことをさらっと句にしているようで、油断すれば、中七「鐘が鳴るなり」で切らずに、下五「法隆寺」と一息に流れて読んでしまいがちです。
① なぜ「鐘が鳴るなり」に感動?――「場」を考える
この句は「柿くへば鐘が鳴るなり/法隆寺」で、「なり」で切れます。そこに作者の感動があるのは明らかです。では作者は、なぜ鐘が鳴ったことに感動したのでしょうか。それは「柿くへば」という上五と関係します。脊椎カリエスの療養後、故郷の松山から帰京の途中に訪れた奈良法隆寺。子規の病状からすれば一時の回復であったのですが、この回復の瞬間を子規は謳歌している趣があります。「古都奈良で、それも法隆寺で、奈良の特産の柿を頬張ったら、なんとどこからか鐘が鳴ったではないか」というこのお誂え向きのような偶然に対する素直な驚きと喜びが句全体からあふれています。鐘の音の響く澄み渡った秋空、色ずく柿、落ち着いた古都の風情、奈良のすべてが自分を歓迎してくれているような瞬間です。古都奈良への挨拶の句でもあるのでしょうね。大らかで明るくて、どこかしらユーモアさえ漂っています。
② なぜ「なり」?――調べと心情を考える
「鳴るなり」には、「なる」「なり」という一種の同音反復的な趣があります。この反復が、秋空に鐘が鳴り渡る、「鳴るなり」という同語反復的な余韻をもたらし、この句の大らかさや大きさを生む一因となっているとも思われます。
では、中七「鐘が鳴るなり」を「鐘の鳴りけり」とすればどうでしょうか。文法的に考えれば、断定と詠嘆の違いです。「けり」は、気づき・発見の「けり」とも説明されることが多いのですから、子規の心情に即せば、ここでは「けり」が成立するようにも見えます。しかし、あえて、心情を直接表す「けり」ではなく、単なる断定で言い切るところに句のセンスが感じられます。作者の過度の思い入れは、句の鑑賞にとっては押しつけがましさにつながりますし、むしろ読み手の句の鑑賞を狭める可能性さえもあります。これも心情に関して説明的であるということなのでしょう。
| 前のページへ | 1/2/3 | 次のページへ |
| ● 「秋三句」の指導案をダウンロード | 一太郎版 |