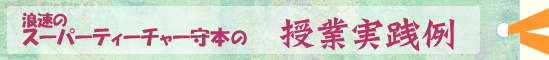|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 前のページへ | 1/2/3 |
c 啄木鳥や落葉をいそぐ牧の木々 水原秋桜子
この句について秋桜子自身が「明るい外光を取り入れた」句としています。なかなか難しい表現ですね。光の描写など一切ないのですから。したがって、この句に「明るい外光」を感じ取るのが授業の目標のひとつになります。
① 作者の視点は?――「場」を考える
まず、作者の視点について考えていきます。作者がどこでこの句を作ったのかを考えるということは、具体に寄り添うということでもあるのです。
まず、「牧の木々」とあるのですから、木々が見渡せる場所に位置しています。「牧」という大きな捉え方がそれを裏付けてもいます。「啄木鳥や」というのは、啄木鳥がその嘴で木をつつく音を聞き、啄木鳥を思いやっているということでしょう。
この音については一つの効果があります。「閑かさや岩にしみいる蝉の声」(松尾芭蕉)、「薪をわる妹一人冬籠」(正岡子規)の例を出すまでもないのですが、「音」が強調される状況は、基本的に静寂な空間であることを示すという逆説的な効果があるのです。音の強調は静寂性の強調でもあるのです。したがって、この句の空間も「啄木鳥が嘴で木をつつく音が響き渡るほど静かである」ということなのです。
「牧の木々」が視界にあるのですが、その木々の「落葉」が見えるところに作者はいるのでしょう。そして、どこかしら「啄木鳥」の木をつつく音が聞こえてくるという奥行きのある空間が見えてきます。前景に「木々」が連なり、その向こう側に「啄木鳥」が潜む、より大きな空間。そしてその音が響く空間は澄み切った秋の空の下にあるということでしょう。ここに季語の効果があります。そう考えれば、この空間には「秋の光」は欠かせないように思えますね。
② なぜ「啄木鳥や」?――「切れ字」を考える
「啄木鳥や」と切れ字があるため、そこに感動の中心はあるといえるのですが、この句には二物配合、いわゆる「取り合わせの句」の趣があります。「取り合わせの句」とは、「二つの素材を並べ置くことで生まれた発見や驚き、取り合わせの妙を主眼とする句」のことを言います。したがって、二つの素材のどちらか一方に感動の中心があるとは言い切れないところがあるのです。一見すれば関係のないもの同士を結びつけて、そこに新たな関係を発見する、また、その場にいる誰もが気づかなかった二つのものの関係を見て取るということは、座の文芸としての俳句の醍醐味のひとつともいえます。
「啄木鳥」と「落葉」との関係について教室で考えていますと、「木々から葉々が落ちるのが、啄木鳥の木をつつく音のリズムと呼応している。」という答えが返ってきます。多分そういうことなのだと、まずはそれを指摘した生徒を褒めるのですが、その次に、それなら、「啄木鳥に落葉をいそぐ牧の木々」でもいいのでは? と投げかけます。これは、なかなか難しい質問です。すぐには答えは返ってきません。ここに、「取り合わせの句」と「切れ字」のヒミツがあります。
「降る雪や明治は遠くなりにけり」(中村草田男)のように「切れ字」が二つある(「や」「けり」)句も珍しくありませんが、それらは基本的に「取り合わせの句」であり、二者を説明的に並べるのではなく、それぞれを独立したものとして並列するために「切れ字」が用いられている場合が多いのです。「降る雪に明治は遠くなりにけり」では「降りしきる雪を見ていたら、遠い昔のことを思い出したなあ」という説明になってしまいます。しきりに降る雪の感動と、明治を懐かしむという心情の取り合わせそのものに深い感動があるのですから、二者を切り離す必要があるのです。つまり、「降る雪や」とすれば、ここに「切れ」が生まれ、「降る雪や」は独立して、季語としての「雪」が機能し、しきりに降る雪への作者の感動が見えてきます。ここで「切れ」がなければ、「雪」についての作者の感動は見えてこないのです。
「啄木鳥や」の句にしても、「啄木鳥に落葉をいそぐ」では説明の句になってしまうということです。「啄木鳥が木をつつく音に合わせるかのように木々が落葉としている」というような「啄木鳥」と「落葉」の関係を指摘した観念の句になってしまうからです。
「啄木鳥や」として上五で切れることで、ここに間が生まれ、秋の「牧の木々」をつつくもの寂しげな音をもたらす「啄木鳥」という季語が働いてくるのです。
確かに、啄木鳥の木をつつく音と落葉とは関係があるのですが、それを物語風に説明するのは俳句ではありません。「啄木鳥」という季語の世界と、木々の「落葉をいそぐ牧」が調和的な雰囲気を醸し出しているということなのです。そこを踏まえたうえでこそ、「牧の木々」が「啄木鳥」の音にせかされているように散っていくという発見が生きてくるのです。少し回りくどいようですが、一句の感動を分析にすれば、そういうことに思い至るのです。
③ なぜ「落葉をいそぐ」――心情に寄り添う
この句の魅力に中七「落葉をいそぐ」という擬人法の美しさがあります。落葉がしきりという情景を「いそぐ」という見て取り方に視線の優しさが感じられます。また、この表現には、「木の葉ふりやまずいそぐなよいそぐなよ」(加藤楸邨)の例を出すまでもなく、落葉をいそいでいると見る作者には、いそいでほしくない、散ってほしくないという心情が隠されているのです。つまり、「いそぐ」という語の裏には、「惜秋」の心情があるのです。先述したように、音の響きの表現の裏には静寂があるということと同じように、対象をいそぐと見る心情の裏には、いそいでほしくないという心情があります。これらの表現がもつ陰影の関係の発見は、他の句の鑑賞にも役立つと思います。
冒頭で述べたように、もし、この句に「光」を感じるとすれば、それは秋の陽射しがもたらした陰影によるものかもしれません。光が強ければ強いほど陰影は深くなります。落葉や牧の木々の印象の鮮明さや、惜秋の心情の陰影の深さがこの句に光を感じさせているるのかもしれません。
| 前のページへ | 1/2/3 |
| ● 「秋三句」の指導案をダウンロード | 一太郎版 |