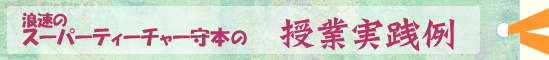|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 前のページへ | 1/2/3 | 次のページへ |
b 海に出て木枯帰るところなし 山口誓子
俳句は論理や説明ではない、と先述しましたが、どうもこの句は説明的です。陸地から海上に出た「木枯らし」はゆく当てがなくなる、ということなのでしょう。実際の情景というより、むしろ観念的にさえ見えます。この句を詠んだ時期(昭和19年)、誓子は療養のため伊勢に滞在していたのですが、この句には伊勢の海岸の冬の光景が見えません。海に出た木枯らしという景色が具体として浮かんでこないのです。俳句が座の文芸であるとしたら、この句は失格です。しかし、それ故にこの句は「座」から離れた近・現代俳句といえるのです。
このような教師側のとまどいとは裏腹に、生徒は、特に男子生徒はこの句を好みます。観念的で虚無的、それでいて感傷的というのが、この時期の男子には寄り添いやすいのでしょう。
①なぜ「帰る」?――表現に寄り添う
この句の下敷きとなった句に、江戸談林派であった池西言水(いけにし ごんすい・1650~1722年)の「こがらしの果てはありけり海の音」があります。和歌や俳諧では、よく「春の行方」に思いを馳せるのですが、言水は「木枯らしの行方」に思いを馳せ、それが遠くの海鳴りに変じるというところを諧謔としているのです。少し理屈が勝っているようにも思えますが、理知の持つ明るさがそれとなく漂っているとも言えます。それに比して、誓子の句には、言水とは正反対の現代的な寂寥感・孤独感が漂っています。
寂寥感や孤独感が主題で、陸から海に吹き込む木枯らしがゆく目当てを失ってさまようということなら、「海に出て木枯らし向かふところなし」でも、言水を踏まえて「果てはなし」でも良さそうです。それを「帰るところなし」としたところにこの句のヒミツがあるのです。
大体、「木枯らし」に帰るところがあるというのがおかしいのですが、その「木枯らし」に帰るべきところがあるとしたところに誓子の発見があり、言い放しで虚無的に見えるこの句の唯一の救いがあるのです。水原秋桜子の「啄木鳥や落葉をいそぐ牧の木々」の解説で記したように「落葉をいそぐ」という表現には、いそいでほしくない心情があります。また、加藤楸邨の「木の葉ふりやまずいそぐなよいそぐなよ」の場合にも、療養中の作者の心情が深く投影されているように、この場合の「帰るところなし」という表現には、「木枯らし」には帰るべきところはあるはずであるし、帰ってきてほしい、という思いが秘められているのです。つまり、「木枯らし」が帰れるかどうかに注目しているといえるのです。
生徒たちはこの虚無的な感傷に関心を持つのですが、この心情がどこからくるのかは理解できません。そこで補助線です。
②補助線を引く――「場」を考える
この句は、戦時下の昭和19年11月の作で、誓子はこの句を、戦後に自ら解説して、特攻隊を悼んで作った句としています。つまり、帰ることを許されない特攻隊員が戦時の空に飛び立っていく姿を、帰るところない「木枯らし」に重ねているというわけです。確かにこの説明を受けると、この句はとてもわかりやすい句になりますね。生徒も、句を覆う寂寥感や孤独感、先述した「木枯らし」に帰るところをありとする心情に根拠を得て、ようやく句に寄り添えることができるようです。やはり、「場」の理解によって句が成立しているということなのでしょう。
実は興味深いことに、この句は発表当時から、読み手に特攻隊のことを喚起させていたようで、作者の解説なしでも特攻隊を悼む句として人口に膾炙していたのです。戦後の作者の解説は、それに対する追認に過ぎなかったのです。昭和19年という時代状況が、人々に共通の心情をもたらし、「場」として成立していたというわけです。切実な緊張感のある時代がもたらした句と言えます。
| 前のページへ | 1/2/3 | 次のページへ |
| ● 「冬三句」の指導案をダウンロード | 一太郎版 |