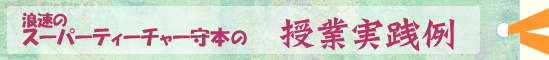|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 前のページへ | 1/2/3 | 次のページへ |
b 万緑の中や吾子の歯生え初むる 中村草田男
①「万緑の中や」――「取り合わせ」を押さえる
「万緑」という季語を定着させた有名な句です。なぜ「万緑や」と上五で切らずに、中七途中の中途半端な「万緑の中や」なのでしょうか。これがこの句のヒミツです。
まず作者の位置を考えていくと、「万緑や」では滴る新緑溢れる光景を前にした印象が出てきます。しかし「万緑の中や」になると、はっきりと新緑に囲まれていることがわかります。「万緑」という季語にもそういうニュアンスはあるのですが、やはり新緑に囲まれているということを強調し、「吾子の歯生え初むる」と取り合わせようとしているのです。
取り合わせの句には「対比」があることが多いことを先述しましたが、この句もそうです。空間的には「万緑の大自然」と「子ども」、色彩的には「万緑」と「歯の白さ」が対比されています。大自然の緑と小さな子どもの口元からのぞく汚れのない白い小さな歯。子どもは力一杯泣いているのかもしれません。それとも笑っているのでしょうか。自然の生命力あふれる「万緑」に囲まれたとき、その自然の生命力に引き出されたように子どもの「歯」が生えたのです。それは偶然なのでしょうが、我が子が自然と一体になったような感動、我が子が大自然に祝福を受けたような喜びがそこにはあります。それが対比的に描かれることで印象を鮮明にしているのです。
また、「万緑や」に比べ、「万緑の中や」は五七調ではなく、かなり散文的です。「松島やああ松島や松島や」というように五七五の調べにのせれば何でも俳句的に響くのですが、それが逆に俳句を通俗的なものにし、句の本質を見誤らせていることがあります。この句は「万緑の中」の強調によって散文的になることにより、五七調の持つ通俗性から脱し、斬新な内容にふさわしい、新しい響きを獲得しているといえるのです。とはいえ、切れ字を用いているところに、やはり散文ではなく、韻文としての俳句へのこだわりが見えます。
②「吾子」――特殊から普遍へ
散文的な調べとともに、この句には俳句的でない特徴がもう一つあります。「吾子」という表現です。俳句では「吾子」という表現はそれほど一般的とは言えないのです。例えば、我が子を扱った中村汀女の「あはれ子の夜寒の床の引けば寄る」「咳をする母を見上げてゐる子かな」も「吾子」ではありません。俳句においては、視点は常に「自分」にあることが前提ですから、「子」は「我が子」を指すのは当然であり、あえて「吾子」とするのは短詩形にとっては無駄であり、蛇足でもあるのです。それでもなぜ「吾子」なのでしょうか。これがこの句の二つ目のヒミツです。
草田男は人間探求派といわれています。昭和十年代という安穏としてはいられないような時勢もあったのでしょう、伝統的な花鳥風月を対象とするホトトギス派への反発もあり、社会や作者自身の境涯を句の対象とします。そこには、人間に焦点を当てることでその背景である社会を描くという意図もあったのでしょうが、特に作者自身の境涯を探求することで、社会や人間の本質に迫ろうとしたのです。徹底的な個人への探求こそが普遍性をもたらすという逆説がそこにあります。短詩形という制約を持った俳句が普遍性を獲得するためには、逆に個人の探求を通じて人間の本質を描き出す必要があるということなのです。
この句の場合も、作者の実感はまさに我が子に起こったことに根ざしています。この奇跡のような自然との一体感、自然からの祝福は、自分の子どもに起きたことだからこそ手放しに嬉しいのです。自分の実感に忠実であろうとすれば「吾子」になるというわけです。個人という特殊に起きたことを追求すれば、すべての人に共通する普遍に到達するという思いが「吾子」という語に集約されているのです。
| 前のページへ | 1/2/3 | 次のページへ |
| ● 「夏三句」の指導案をダウンロード | 一太郎版 |