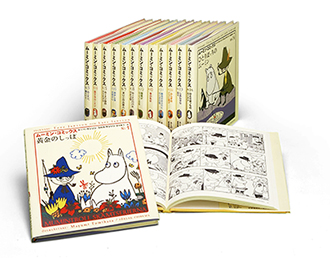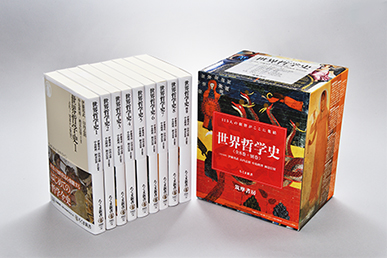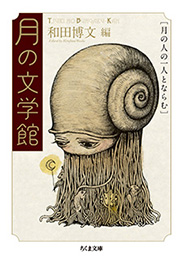志賀信夫
( しが・のぶお )志賀 信夫(しが・のぶお):宮崎県日向市出身。大分大学福祉健康科学部准教授。一橋大学社会学研究科博士後期課程修了、博士(社会学)。NPO法人「結い」理事。専門は、貧困理論、社会政策。「貧困とは何か」について研究し、いのちのとりで裁判において意見書を執筆、大阪地裁、岡山地裁に有識者証人として出廷。著書に『貧困理論の再検討――相対的貧困から社会的排除へ』(法律文化社、2016年)、『ベーシックインカムを問いなおす――その現実と可能性』(共編著、法律文化社、2019年)、『なぜ基地と貧困は沖縄に集中するのか――本土優先、沖縄劣後の構造』(共著、堀之内出版、2022年)、『貧困理論入門――連帯による自由の平等』(堀之内出版、2022年)、『漂流するソーシャルワーカー――福祉実践の現実とジレンマ』(共編著、旬報社、2024年)などがある。