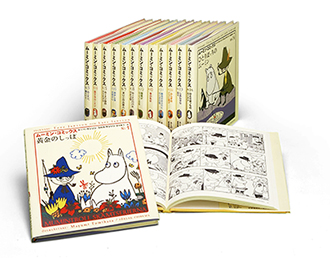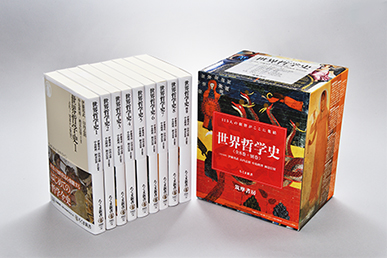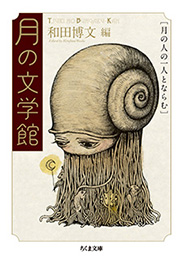上流で大雨……
ここは降っていなくても危険!
頭上の雨だけを見ていても水土砂災害は分からない。雨は「流域」で集められ、災害を引き起こすからだ。身を守るために、予想以上の雨が日本列島を襲っている今こそ「流域思考」を身に着けよう!
「流域思考」とは?
雨の水を川に変換する大地の構造のことを「流域」と呼びます。豪雨が引き起こす水土砂災害は、大小のスケールにかかわらず、「流域」という地形や生態系が引き起こす現象です。日本の利用可能な土地はほぼ河川の流域に属しており、流域は行政区域に関係なく広がっています。行政によるハザードマップだけではなく、この「流域」を枠組みとした「流域思考」を知ることで、豪雨による災害にきちんと備えることができるようになるのです。
===
近年、水土砂災害が急増した第一の理由は、強い雨が増えていることです。これからの50年、100年、200年にも及ぶ深刻な地球温暖化の表れだという意見も有力です。現状は、数十年間隔の気象変動のレベルという解釈も完全に否定されているわけではありませんが、いずれにしても、ここ10年の動きを見ていると、今までの常識では対応できない豪雨が増えていることは事実です。
この傾向はこれからも続くと考えておくべきでしょう。わたしたちは、すでに温暖化豪雨時代の入り口にいるのかもしれない。そう判断し、対応していくほかないと、思われます。
ところが、現状はその緊急事態とも言える状況に、社会が長きにわたり、適切に対応できずにきたのです。一般社会のレベルだけでなく、報道や自治体のレベルでも同じことが言えるのです。
――「長いまえがき〈なぜいまこの本を出版するのか〉」より