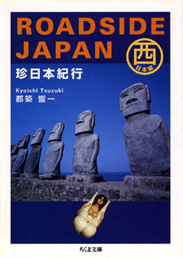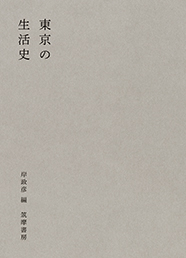

第30回
2014/11/12
最終候補四作品の中で明らかに『コンとアンジ』だけが異質な空気をまとっていた。それは痛々しいほどの警戒心を放つ、未成熟な野生動物を連想させた。安易に読み手にすり寄ってなどいかないぞ、とでもいうような緊張感が一文一文にみなぎっていた。その緊張感を私は好ましく感じた。
主人公がたどり着いた国はどこなのか、旅に出る前の彼女はどんな暮らしをしていたのか、兄はなぜ行方知れずになったのか。本来なら物語の枠組みとなるべき説明を、作者は一切していない。読者にとって必要な情報を提供しようとしない。何かを書くより、書かないでいることの方がずっと難しい。親切にあれこれ説明しておけば、とりあえずは安心なのだ。しかし作者は最後まで不親切を貫いた。その勇気こそが才能の証明だと思う。
おとぎ話では、おじいさんとおばあさんの名前も住んでいる地名もなれ初めも説明がないままに、二人は川で桃を拾うことになる。余分な飾りを極限までそぎ落としたむき出しの言葉は、自由奔放に振る舞い、物語の輪郭を柔軟に押し広げてゆく。だからこそ、桃の中から子どもが生まれても奇妙に思わない。『コンとアンジ』にもこうした物語が本来持っている、混沌や不合理を丸ごと飲み込む底知れない器の大きさがある。器の底では狂気を帯びたカーニバルが渦を巻いている。
どんな時も理屈に従おうとしない主人公は、無防備にも渦の中へとずんずん沈み込んでゆく。言葉の通じない異国の、まがまがしい雰囲気や鬱陶しいほどのエネルギーを、直接肉体で受け止め、肉体が命じるとおりに動く。自分が求めているものは何なのか、自分でも分からない不安を心のどこかに閉じ込め、目の前に現れた睡眠薬強盗のアンジをただひたすら好きになる。強盗されるだけでは足りず、性を偽って苦労して得た報酬さえ惜し気もなく貢ぐ。ついには赤ちゃんまで産んでしまう。
初めてアンジを意識する瞬間の描写が印象深い。
〝……先輩が後ろから顔を出し、包帯の腕を伸ばし、子供ら二人は同時に吸いこまれた。ふわりと。抱き上げられたって感じで。このときこちらの魂も。吸いこまれたにちがいない〞
彼女の危なっかしい不器用さは、放っておけない魅力を発している。彼女が背負う、どうしても移動せずにはいられない衝動には、愛おしささえ感じる。もちろんアンジのことも忘れてはならない。生き残るため、善悪の境など軽々と飛び越えるアンジはセクシーだ。彼にのめり込んでゆく主人公を、私はいつしか応援していた。悲惨さの中でもがく登場人物たちから、作者は人間の本質的な滑稽さをすくい上げ、そのことで人間を肯定しているように思える。
唯一引っ掛かったのは、ラストの12章だった。混沌とした底なし沼に全部投げ捨てて終わりにするやり方が、果たして最善なのか。〝のしのし歩こうと思う〞とつぶやきながら、永遠運動の回し車に足を掛ける彼女の、狂気をあぶり出すようなラストを味わいたかった。そんな思いが残った。
『コンとアンジ』を読み終えて改めて驚いたのは、この作品が〝生まれて死ぬあいだになにを入れる。自分なら〞というあまりにもありふれた問題を扱っている点だった。古典的なテーマを持っているにもかかわらず、他の誰も真似できない独自の世界を描ききっている。言葉の力により、最も遠い場所まで私を運んでくれた受賞作に、拍手を送りたい。
『深夜呼吸』の夜の描写が今でも忘れられない。
〝この夜の中では、誰もかれも、何もかもがとても小さい。等しく、小さい。だから怖がる必要はない〞
白い人に導かれ、桐野が夜の世界の境界線を踏み越えた時、何か魅惑的な転調が起こるに違いないという予感がした。ところがそこで私を捕らえたのは、「見ず知らずの未成年を親にも知らせず家に泊めるのは、犯罪ではないのか」という野暮な疑問だった。
そんな疑問など浮かぶ間もなく読み手を引きずり込む何かが、やはり必要だったのだろう。桃から生まれた赤ん坊をすんなり認めさせるだけの力が物語にはあるのだから、その何かを見つけるのは決して難しいことではないと思う。
犯罪の心配に惑わされる夜の世界より、日常にまみれた家での情景の方が私にはむしろ面白かった。特に、無神経な言動で主人公を傷つけるおばあちゃん。たいこまんを一個だけ買うのが恥ずかしくてつい二個買ってしまい、食べきれなかった分を主人公にあげる場面は素晴らしい。結局、物語の輪郭を広げてゆく力を持っているのは、砂漠で行方不明になったすみれさんの恋人ではなく、一個のたいこまんを買う勇気のないおばあちゃんではないだろうか。
『こぐまビル』で威力を発揮していたのもまた、同じく老人、主人公の祖父である。困難な現実を「あらよっと」の一言でかわし、どうやって生きたらいいかわからないと悩む孫に、「おじいちゃんにもわからん!」「しかし生きとる!」と答え、「飲んでしまえ。世界なんぞ」と言いながらぶどう酒を飲み干す。この祖父の大らかなユーモアが本作の土台を支えている。
他の登場人物に対しても、おじいちゃんと同じ親しみを感じたかった。しかし幸彦もトビーさんも本多さんも主人公も、どこか人間くささに欠けていた。家族を失った人にどう寄り添ったらいいのか、という明確な設定がまずあって、そこに人物を上手く当てはめていった印象が残る。その手順が透けて見えてしまったのかもしれない。
『ジンクレールの青い空』は、どうにも憎みきれない小説だった。ゼロ戦を修理し、空母レキシントンに突っ込むという滅茶苦茶な展開ながら、主人公の軽さに乗せられ、否定しきれないままついすべてを許してしまう、そんな感じだった。
最初から最後まで、仁駈の、男の子らしいふざけたいい加減さが炸裂している。入浴介助の時、じいちゃんたちの体を洗うついでにくすぐって悪戯する彼が、たまらなく可愛らしい。老人たちのはしゃぐ声や笑い顔が、浮かんでくるようだ。介護施設の描写も、地に足がついていた。
だから余計、戦争体験の問題についてはもう少し慎重になってほしかった。彼ら一人一人が抱える事情を明らかにし、説明することでストーリーを動かしてほしくなかった。そうした作為が、せっかくの主人公の魅力を半減させている気がした。
事情などいちいち説明する必要はないのだろう。小説は元々、辻褄が合わないものなのだから。