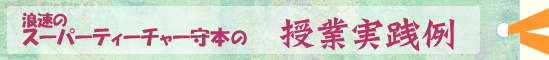|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 前のページへ | 1/2/3/4 | 次のページへ |
② 補助線を引く――近現代人と死
李徴は、なぜこれほど詩に執着したのでしょうか。これもヒミツのひとつです。冒頭に「下吏となって長く膝を俗悪な大官の前に屈するよりは、詩家としての名を死後百年に遺そうとした」とあります。また、これを裏付けるものとして、虎になった李徴の言葉に「おれの詩集が長安風流人士の机の上に置かれているさまを、夢に見る」とあります。文名や作品を遺すことが目的だというのですね。これはわかりやすいようで、捉えづらい感覚です。
そこで補助線です。『高校生のための哲学入門』(長谷川宏 ちくま新書)では、死についてこう述べています。
個人は死に、共同世界は存続する。個として世界を生きる人間にむかって、一方が死に、他方が存続するというちがいが、解きがたい矛盾、克復しがたい矛盾として鋭くせまってくる。死が意識に引っかかり、すんなりとは受けいれられないのはそのためだ。
個人が共同体との一体性を喪失した近代では、前近代のように自分が属していた共同世界の存続を自分の存続と捉えるような心性もまた喪失しているのです。つまり、私たちの死の恐怖は、属していた共同世界からの孤独な離脱という不安に根ざしているのです。また、長谷川氏は同書でこう続けます。
肉体の死がそのまま共同の世界における自分の存在消滅のときだというのが、素直に納得できないのだ。納得できないから、形を変えて自分が存在しつづけるさまを想定する。自分のやったこと、やろうとしたことは、人びとに引き継がれて存在しつづける、とか、自分の生前のすがたや志が身近なだれかれの心に思い出として保たれる、といったように。
死によって共同の世界から自分だけが離脱するという恐怖、自分が離脱しても共同の世界は存続するという承服しがたい実存の矛盾と孤独感から逃れるためには、その共同の世界に自分が存在したという証が保険として必要だということなのです。それはあくまでも死ぬことを運命づけられたものの気休めにしかすぎないのかもしれせんが、それを生きるよすがとせざるを得ないという切実な思いが、詩人としての死後百年に名前を遺そうという李徴のモチベーションとなったことは確かだと思われます。ここにも近現代人としての李徴の横顔が見えています。
おれの中の人間の心がすっかり消えてしまえば、恐らく、そのほうが、おれはしあわせになれるだろう。だのに、おれの中の人間は、そのことを、この上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、まったく、どんなに、恐ろしく、哀しく、切なく思っているだろう!
虎になった李徴が恐れていたのは、死そのものではなく、人間としての自分がなくなることであったというのも、これで理解できます。共同の世界からの離脱を恐れているのです。共同の世界からの離脱こそが人間としての死なのですから。
このように李徴を近現代人として見ていくと、人の性情を猛獣とし、人を猛獣使いと捉える李徴の考えも、感情を統御する理性的な存在としての人間という近代合理主義の考えと合致します。つまり、感情を統御できない近現代人としての李徴の苦悩という視点でもこの作品にアプローチできるというわけです。
| 前のページへ | 1/2/3/4 | 次のページへ |
| ● 3 『山月記』の指導案をダウンロード | 一太郎版 |