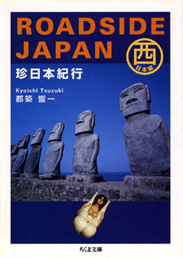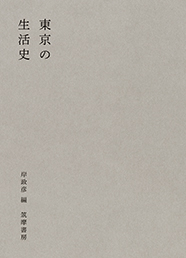

第30回
2014/11/12
このところこの賞は元気がよい。応募数は一一四九編で、今年もだいぶレベルの高い作品が集まった。選考はなかなか充実していた。
秋野佳月さんの「ジンクレールの青い空」は高校を卒業したばかりの介護ヘルパーの若者が主人公だ。仕事場について、「小学三年のときにオープンしたコンビニが、中三のときにレンタルビデオ店になって、高三で就活はじめた頃には、サポートハウスともしびの看板に変わっていた」とある。現在の高齢化社会が作りだした、介護サポートという新しい仕事の場で、世間から脱落しかかった老人と、やはり世間のとば口に立ったばかりの若者が出会う。そんな面白さがうまく取りだされている。介護の現場の実際、作品の後半にでてくる飛行機の操作の細部の記述なども地に着いている。しかし、友人、家庭、仕事、学校、すべての設定に恣意的なゆるさがある。小説を書くことのなかには、自分が勝手に作ってしまった設定に逆に拘束される、その不自由さからしか生まれてこない力というものがありそうである。それがないためか、どこかしら、通俗小説っぽい。私には、特に、後半、ハウスに通う元零戦乗りだという山本老人とその友人、加藤さんをめぐる零戦と特攻という主題を扱う手つきが、甘すぎて、軽いと感じられた。じいさんが特攻隊? その安易さが、この作品のなかで「浮いていない」。そのことに(よくも悪くも)この作品自体の積み荷の軽さがよく現れている。
寺地はるなさんの「こぐまビル」の主人公、三〇歳の女性恵さんは離婚の傷を負っている。祖父のもつビルの一室を借り、そこに住みこみ、管理の仕事につく。その合間、祖父に頼まれ、やはり数年前からビル内に住む一〇歳年下のひきこもりの従兄弟、幸彦を、嫌がらせを連発するという奇策を弄しつつ、何とか世間に引きだそうと苦闘する。その一方で、ビルのテナントの刺繍屋のトビーさん、骨董屋のゆり子さん、祖父のビル管理の税務事務を担当する本多さん、幸彦を慕う若い女性野木未来などとのゆるやかな「こぐまビル」の日々の交遊が語られる。全体がゆったりしている。こぐまのように。主人公の人となりの作り方に「遊び」のようなものがあり、こぐまビルという「場」の広がりが描けているところなどもこの作品のよいところだ。ただし、よい意味での安定があり、それがこの小説を安心して読めるものにしている反面、やはり少し浅くもしている。みんな死んでいく。トビーさんも、ゆり子さんの夫も。悲しみが主人公に押し寄せる。それなのに、小説の中心にいるおじいさんは元気なまま。そのあたりに、このお話の安定ぶりとまた物足りなさがよく出ている。小説というのはここから先、どこに行くのか、ということなのだろうか。
橙貴生さんの「深夜呼吸」では、お母さんが幼い妹を連れて家を出て行くところから作品がはじまる。やがて、親の離婚へと進んでいく日々を取り残された一三歳の女の子の目の位置から描いている。中心に罅の入った、安定から遠ざけられた作品の重みがある。中学生。自分で弁当を作り、学校での不安定な友達とのやりとりを何とかこなしていく。そのあたりの心細い情景の記述に読み手を引き込む力がある。何とも冷たく優しさのかけらもないおばあさんの登場にもリアルな感触がある。その後、夏休みとなり、一転、世界はどこかファンタジックな現実離れした夜の世界に移行していく。その前半から後半への飛躍も、危ういながら、小説の構造上、昼から夜へ、日常から非日常への変転と受けとると、それなりに破綻なく読むことができる。しかし、最後、お母さんが出てくるあたりから、親というのはそんなものだろうか、そう思い切るにしては、何か一三歳の主人公に、惨めさ、切なさ、苦しさが足りないのでは、というような感想が浮かんでくる。親子って、こんなに淡泊か、とでもいうような。この親子の関係の味気なさが後半の非現実感を行き場のない中途半端なものにさせている。すみれさんとのクールな日々が心地よく読めていただけに、そこがやや残念だ。そのすみれさんが、最後、現実にめざめる展開も、もう一つ工夫ができなかったか。このため、前半と後半の対比がぼやけ、世界変転のカギとなる「白い人」の存在が、宙に浮いてしまった。
これら三作は、なかなかよかった、と同時に、どこか既視感のあることも否めなかった。これに対し、最後の、井鯉こまさんの「コンとアンジ」には、まったく違う、選考委員を元気にさせる「活気の素」のようなものがある。面白い。これだけの「自由」さの展開は受賞に値する。私は迷わずにそう感じた。
舞台はどこともしれない外国。なぜここに主人公はいるのか。これもわからず。そのうえ、これまでの三作にくらべてこの作品は安定した語りに欠けている。ぶつぶつと文章は切れる。しかしある種のダイナミックなうねりがあり、その読みにくいリズムと、説明のなさ、思いっきりのよさが、読み手を引っ張っていく。私は、この引きこまれ方に町田康氏の「くっすん大黒」を少し、思い出した。
舞台は、日本ではなく東南アジア。どこの国かということはわからないが、これはむしろ、周到にわからないように設定されているのかもしれない。主人公は、女性なのだが、途中から男装して現地の怪しげな「マソン商会」で一四歳のブータン人と偽って働く。話されるのは現地語。日本語が特に前半では完全に奪われているのが新鮮だ。それだけではない。気づくと、日本人であることも、女性であることも、年齢も、すべて奪われている。小説全体が、二階に上げられ、梯子をハズされている。というか、自ら梯子を外し、これまでにない「自由な言語体験」を日本語で実現している。去年も似た感想が浮かんだが(「さようなら、オレンジ」)、それとは違う意味で、やはりこういう小説も、これまでになかったのではないか。私の数少ない経験では、日本人として東南アジアのいくつかの国に滞在したときの、自分の身体と文化性の輪郭が、現地の懐かしくも生ぬるい空気のなかに溶け出してしまうような体験。その原質が、この小説に表現されているのだと思った。昔見た、沖縄出身の監督高嶺剛の傑作『パラダイス・ビュー』の異化作用に似たものを、この作品からも感じる。
後段、日本人の知り合いが唐突に出てくる。そして話は急転する。そのあたりの現地での友人ジェシカと手に障害をもつ女装の恋人アンジとの関係など、他の委員の指摘に、私は迂闊にも気づかないままだったのだが、それでも、最後まで、勢いで読まされた。
欠点はあるだろう。しかし、これだけの「自由」の強度はただものではない。まぎれもなくおぎゃあと生まれたばかりの「小説」の輝き、力。一人の小説家がここにいるのだと思う。