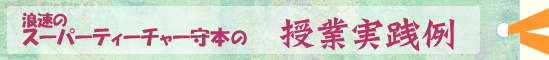|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 前のページへ | 1/2/3/4 |
④ まとめとして
この小説は、主人公の悲痛な独白で締めくくられます。
「父ちゃん、父ちゃん、父ちゃん……。」という叫び声が聞こえた。私の子供たちのようでもあったし、ちがうようでもあった。この雑踏の中の、何千という子供たちの中には、父親の名を叫んで呼ばなければならない子供がほかに何人いたって不思議ではない。
大人たちはだれも気付かないけれど、私たちの周りにはこのような悲劇があちこちで起きているかもしれないというこの結びは、とても不気味で印象的です。自分たちが捉えられない世界が自分たちの世界と並行して存在し、その世界への見えない落とし穴がぽっかりと私たちの世界に用意されているのです。そこに落ちなければ見えないけれど、落ちてしまったらそれが最後という悲劇の落とし穴です。読み手に言いしれぬ不安と不気味さを感じさせます。
『待ち伏せ』でも述べましたが、現代小説は、世界と自分との違和感・ねじれ感を主題とすることが多いのですが、この小説の不安感はそれにつながるものだと思います。
もう一つ、この小説で忘れてはいけないことがあります。それはユーモアです。安部公房の作品にはどこかしらユーモアが用意されているのですが、全体的な不気味さと自分の現実を否定されるような不安感により、なかなかそれに気付くことができません。手探りで読み進めている生徒にはそれを味わう余裕がないのです。一通り授業が終わり、もう一度読み直すことを生徒に勧めますと、生徒は新たな発見をします。
「先生、ひげが……。」どうやらそのひげは付けひげだったらしい。左端がはがれて、風でぶるぶるふるえていた。先生は静かにうなずき、指先につけたつばでしめしておさえつけ、何事もなかったように両側の学生をかえりみて言った。
地上の世界に変装してやってきた「裁く側」の「先生」の描写です。時代遅れの、絵に描いたような教師と生徒の変装とその仕草に滑稽味がありますね。次は、「先生」が生徒に質問してその答えを待っている時の様子です。「先生」は、主人公が変身した例の「棒」をもっています。
先生は、私をとって、地面になにかいたずら書きをしはじめる。抽象的な意味のない図形だったが、そのうち、手足が生えて、怪物の姿になった。つぎに、その絵を消しはじめた。
生徒に発問し、その答えを待つまでの手持ちぶさたの教師の手慰みです。無意味な図形を落書きしていると、意図せず具体的な物に見えてくることがありますが、先生はそこに怪物を見出だしているのですね。ある意味ほほえましい、よくある教師の姿のように思えてきます。
大事なことは、これらのそれとないユーモアが、この小説にリアリティーを与えているということです。このような現実離れした小説こそ細部のリアリティーが要求されるものですが、作者はそれにユーモアをもって応えているのです。たとえブラックユーモアにしても、笑いには読み手を作品世界に引きつける力ありますし、そこに説得力を与えてくれるようです。現実離れしたSF的な世界を描くことが多い作者の作品にユーモアが不可欠な理由もそこにあると思われます。この作品に限らず、笑いやユーモアが授業でより注目されてもいいように思いますね。
| 前のページへ | 1/2/3/4 |
| ● 2 『棒』の指導案をダウンロード | 一太郎版 |