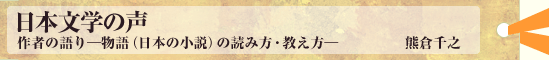|
|||||||
|
|
|||||||
| 前のページへ | 1/2/3/4 |
④作者と主人公の切っても切れない関係――作者の「暗黙知」としての物語
こんなに言語能力に優れた人物を、ただの宿屋の女将にしておくのは勿体ない、という意味では、この物語の語り手には実在感がないかもしれない。それほどまでに、三浦哲郎という作者が、女将の語りに寄り添っているからだ。ここで「声」を発しているのは、この物語を仮構している作者なのだから。
作品を意味あるものにするために、作者が女将に敢えて「冒険」させ、その倫理の是非を問うている。『とんかつ』という小説が「お互いの温かい心」を描きたいのなら、入門後は「精進揚げ」でも事足りよう。しかし『とんかつ』の主題は、〈修行中の身〉に敢えて禁制の「肉食」を薦める主人公の、倫理観を世に問うことだ。むろん世間の批判を覚悟の上であり、女将(作者)は戒律の厳しい曹洞宗の掟(権威)に対して、挑戦(冒険)的な行動をとったことになる。だから、「修行僧を堕落させるに等しい女将の行動は倫理性に欠ける」という常識を否定するのは、作者の「暗黙知」――読者に探させるために、作中に敢えて文章化しない叡智――だ。推理小説を原型にもつとされる「小説(物語)」では、わざとその「意味(主題)」を隠して、簡単には見破られないようにするというのが、作者のたくらみだ。ここでは、倫理的「権威」が宗教団体ではなく、個人にあるという主張が、優れて日本的だろう。敢えて言えば、「ポストモダン」でもあるだろう。『とんかつ』の語りのどこにも、主人公に罪障感がない。
「作者の死」――テクストさえ残されれば、誰が何故書いたかなどは考えなくてもいいという主張――は、日本の物語の場合、理想でも目標でもない。これは西欧の小説とは一線を画す大事な違いだ。この作品で作者三浦哲郎は、宿の女将に託して自らの倫理を語った。一人ならず自殺者を出したという、己の家への鎮魂歌として書かれた『みちづれ』を巻頭に置く『みちづれ 短編集モザイクI』は、その第二作として、この『とんかつ』の母子を作者の出身地東北の風土に重ねている。
したがって、「作品論」や「作家論」の有効性を無視した議論は、日本では文学論になりえない。このことは、近現代の日本の文学のあらゆるテクストについて言える。たとえば近代文学の第一人者である夏目漱石の作品の多くが、特に『門』以降の後期の作品が、ことごとく誤読されてきたのは、専門家が西欧の文学理論に「盲目的崇拝」をした結果、中島敦の言う「文字禍」となって、日本語の読み手に本来なら見えるべきものが、見えなくなってしまったからだ。
| 前のページへ | 1/2/3/4 |