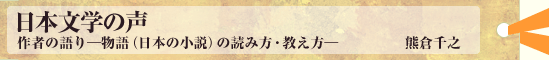|
|||||||
|
|
|||||||
| 1/2/3/4 | 次のページへ |
①日本文学はテクストのすべてが物語
語り手(話し手・書き手)の声しかない日本語の本質として、日本文学のテクストは、すべてが語り手(書き手)の「主観」でできている。いや、「客観」もあるはずだ、なければならない、という主張を、日本人は明治以来百何十年も続けてきたのだが、間違いだった。えっ! と驚く読者は、いまここで、まず自分の声に素直に向き合ってほしい。
西欧語の「客観」は、日本語では望むべくもないのだということが、次第に判ってくるだろう。それは例えば、〈He is happy.〉という英語表現は、〈He〉が〈happy〉という気持ちであることを「客観」的に、〈He〉の「属性」として表現するが、これが日本語に「翻訳」できないのは、日本語の〈うれしい〉が第三者である〈彼〉には使えないからだ。〈彼はうれしい〉が非文法なのは、〈うれしい〉と表現できる主体は話者以外にはあり得ないからだ。それでは、〈I am happy.〉なら翻訳できるかというと、これも心の属性を「客観」的に表す英語の〈happy〉は、日本語の心情がじかに表出される〈うれしい〉とは、意味の質が違う。英語の〈happy〉は〈you〉〈we〉〈they〉どれにも使えて汎用性がある分、誰の「声」も聞こえない。ナマな情意を伝えることばではないからだ。それに反して、日本語の〈うれしい〉には、間違いなく話者の「声」が聞こえる。
日本語で書かれた「小説(物語)」を読む場合、まず語り手(あるいは文章の書き手)の声が聞こえてくる。『とんかつ』の場合――
〈須貝はるよ。三十八歳。主婦。同 直太郞。十五歳(今春中学卒業)。宿泊カードにはやせた女文字でそう書いてあった〉と、語り文が始まる。〈そう書いてあ〉ると認識しているのが宿の主人だと知れるのは、少し先の、〈女中が二人連れの客だというので、出てみると…… 〉の、〈出てみる〉という動作からだ。その時点ではまだ、この宿の主人が男か女かが判らない。それが「女将(おかみ)」と特定できるのは、〈……なんでわざわざこんなとこまで遠出してくるのよ〉とか、〈……死に場所なら、東北にだっていくらもあるわ〉という終助詞(女性ことば)に拠ってだ。因みにこの物語を英訳しようとすれば、一人称代名詞の〈I〉を多用しなければならない反面、語り手の性別をはっきりさせる手段に悩むかもしれない。しかし日本語では、この声のありかで物語の語り手が誰であるかが、ほぼ直感的に判る。
女将は、〈二泊三日とは豪勢な〉と思われる母と子の宿泊目的が、親子心中などではなく、息子が戒律の厳しい曹洞宗の大本山・永平寺へ入門のためであることを知る。そこで息子の最後の晩餐に、入門後は食べられない好物のとんかつを揚げて出す。一年後、怪我治療のため入院している息子に母親が見舞いに来、すっかり修行僧らしくなった息子は、同じ宿屋で再びとんかつを供される。その一部始終を語る女将は、「私」という「自称詞」(日本語に「人称代名詞」はない)を、語りの中で一度も使わない。それが日本語にそなわる「話し手の言語」の特性だからだ。「私」が省略されているのではなく、もともと英語の「主語・述語」の統語法をもたない日本語は、原則的に動作主体は話者だから、わざわざ「私」と言う必要がない。
事実を「客観」的に押さえることを旨としてきた西欧の小説には、作者の声はいらない。テクストは、「外にあるものごとを、外にあるものごととして再現」する機能が備わっているから、作者がテクストに声を出す必要がない。一方、日本語の物語では、語り手の声が常に作者に連動して聞こえるし、そこにこそ物語の意味があるのだ。NHKのアーカイブスに入っている、インターネット高校国語講座の解説者によれば、『とんかつ』の「主題」は、登場人物たち三人が「それぞれお互いに温かい心を通わせ合っていること」だという。それがこの作品で作者が言いたいこと(主題)だとするならば、どんな物語にも、多かれ少なかれ、人物たちの「心の触れ合い」が描かれているのだから、『とんかつ』についても、その指摘だけでは、生徒たちにインパクトを与える、いつまでも心に残る物語とはならない。
| 1/2/3/4 | 次のページへ |