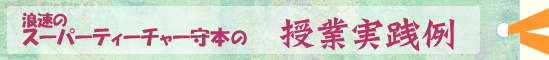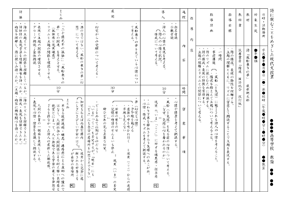|
|||||||
|
|
|||||||
| 1/2/3/4 | 次のページへ |
この詩のヒミツは、「なぜ、宇宙のはてまで?」です。しかし、この詩は難解なようで、普通に読み進んでも、このヒミツにたどり着くのは容易ではありません。そのため、授業で取り上げられることもそう多くはないようですが、それでは、少しもったいない気がします。この詩の現実否定・現実逃避・孤独という主題は、詩に限らず、文学における重要なテーマです。しかも、それらの作品の表現には多くの共通点があり、それを押さえながら丁寧に読み進めていけば、それほど難解な詩ではなく、むしろ、生徒に多くのイマジネーションを喚起するすぐれた作品であることが理解されると思います。
① 具体に寄り添う ―― 幻想(妄想)の根っこ
まず、具体的に場面を考えていきましょう。難解な詩ほど、具体的なイメージがないと読み進められません。
夏草のしげる叢(くさむら)から
ふはりふはりと天上さして昇りゆく風船よ
詩人の位置は限定できませんが、草地から風船(気球)が離陸しているのを、どこからか、「酒瓶の底は空しくなり」とあるので、酒を飲みながら見ています。そして、「ふはりふはり」上昇していく気球に視線を送る中で、詩人の幻覚(妄想)が始まるのです。「ふはりふはり」という繰り返しに、気球に心を奪われ、感情を移入していく過程がうかがえます。
朔太郎に限りませんが、詩人が具体的な対象を凝視する中で、それに入り込み、妄想に近い幻想が始まるとというのはよく見られます。蛸や猫や竹等、詩人がそれらに感情を移入していった時、見えないものが見え、聞こえるはずのないものが聞こえてきますが、それは、細部への凝視から得た発見や驚きに根ざすもので、そこに感情移入した中で起きる時の幻想のなせることです。幻想的で超現実的と思える表現ほど、それがどのような現実、もしくは具体に根ざすものかを考えることが大事なのです。
この詩でも、すでに詩人は半分、風船乗りになって幻想の世界に没入し、大地を離れて上昇していく気球に夢を託し、幻想にふけっています。
籠には旧暦の暦をのせ
はるか地球の子午線を越えて吹かれ行かうよ。
ばうばうとした虚無の中を
雲はさびしげにながれて行き
草地も見えず 記憶の時計もぜんまいがとまつてしまつた。
詩人の幻想は、気球を下界から、子午線を越えて、虚無の中へ飛ばしていきます。その虚無の中では、「記憶の時計」も役立ちません。そこは、下界の月(month)と日(day)の暦(カレンダー)より、月(moon)の満ち欠けが中心の旧暦が役に立つ、天体の世界です。
では、なぜ詩人は下界を離れた虚無の世界を「美麗な幻覚(まぼろし)」として、幻想するのでしょうか?そこで、補助線です。
| 1/2/3/4 | 次のページへ |