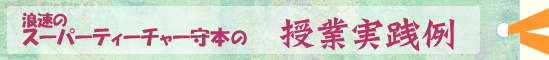|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 前のページへ | 1/2/3/4/5 | 次のページへ |
① なぜ、「技術」が「芸術」と同じ?――二項対立で考える
「技術」の根源について作者はこう述べています。
古代ギリシアにおいても、技術を意味する〈テクネー〉ということばは、同時に芸術をも意味していたのであり、そうした技術=芸術はむしろ自然の働きの一環、ないしはせいぜいそのちょっとした延長と受けとられていたのである。
「技術」と「芸術」の元は同じ、これは難解ですね。具体に乏しすぎます。これを解きほぐしていきます。まず、一般的に二項対立で考えれば、
技術・理性・科学 ⇔ 自然
であり、
技術・理性・科学 ⇔ 芸術
ということになります(「二項対立読解法」については、『教養としての大学受験国語』石原千秋/ちくま新書 に詳しい)。
対立するはずの「技術」と「芸術」を同根とする作者の考えは生徒の常識とは異なるもので、驚きがあります。これが面白いのですね。つまり、
理性 ⇔ 感情・芸術・技術
ということになり、「技術」が「感性」の仲間になってしまうのです。
「芸術とは?」という問いを生徒に投げかけても誰も答えられません。だいたい筆者がハイデッガーを下敷きにしているといっても、ハイデッガーの芸術論なんて教室で扱えるものではありません。だから工夫がいるのです。
私の場合は、ピカソや、ゴッホ・北斎など、比較的個性的な画家を例に出します。「彼らの絵画はなぜかくまで個性的なのか?」という問いです。「芸術家の目にはそう見える?」というあいまいな答えが出ます。私は「じゃあ、なぜそう見える?」と嫌らしく畳みかけます。生徒は「……」。難しいですね。しかし、ここまでくれば答えはすぐそこにあります。
何もゴッホやピカソが、自らが描く絵のように現実の世界が見えているわけではないのでしょうが、芸術家が関心を持つ世界を画布に再現しようとするとき、それを自分の実感を元にして表現し、対象を自らの実感において位置づけようとすればそう表現せざるを得ないのです。あれほどまでにデフォルメして初めて自分の実感に近づいているのです。そういう意味で、「芸術」とは、自分と対象との、または世界との関係を示し、自分が世界をどのような実感として捉えたのか、ということを意味しているのです。
オスカーワイルドの「自然が芸術を模倣する」という有名な言葉がありますが、私たちは芸術家が捉えた実感としての自然や対象を通して、初めて自然の捉え方や見方がわかり、自分と自然がつながっているという実感を得ることができるのです。
そして、「技術」は、世界と実感でつながるという「芸術」と同根なのです。この評論の下敷きとなったハイデッガーはこう記しています。
テクネーはギリシア的に経験された知としての、現前するものを現前するものとして伏蔵性から〔aus... her〕ことさらに〔eigens〕その形姿の不伏蔵性の内へと〔in〕、直前に〔vor〕もたらす〔bringen〕かぎり、存在するものを生み出すこと〔Hervorbringen〕である。けっしてテクネーは作る〔Marchen〕という働きを意味しないのである。
芸術家は、手仕事の職人であるから、テクニテースであるというのではない。そうではなくて、作品をこちらへと―立てること―〔制作すること(her-stellen〕)も、道具をこちらへと―立てること―〔製作すること〕も、共に、存在するものをその形姿からその現前へてあらかじめ出で―来させる―〔vor-kommen〕、あの〈こちらへと―取り―出す〔Hervor-bringen〕〉という仕方で生起するからなのである。
(「真理と芸術」より 『芸術作品の根源』
マルティン・ハイデッガー/関口浩訳 平凡社ライブラリー)
要は「芸術」も「技術」も、「自然」の中にあるが、隠されている「自然(世界)」の「本来の姿」を取り出し、「明らかにする」ということなのでしょう。「芸術」はそれを取り出し、実感として描き、「技術」は製作によってその本来の姿を明らかにしていくのです。両者に共通するのは、「自然」(「世界」でもいいと思います)を明らかにしたい、自分とつながったものにしたい、という感情ということになります。
しかし、それをハイデッガーで説明するのは教室では無理があるので、私はピカソやゴッホを用いて、出来る限り実感に寄り添えるように説明を試みたのです。
また、「技術論」では同じ教科書に掲載されている中村雄二郎の『好奇心 知的情熱としての』に補助線を引きました。
| 前のページへ | 1/2/3/4/5 | 次のページへ |
| ● 「技術の正体」の指導案をダウンロード | 一太郎版 |