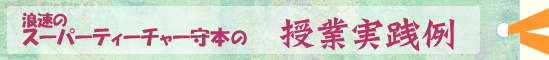|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 前のページへ | 1/2/3/4/5 | 次のページへ |
② 補助線を引く(1)――なぜ、人は旅をする?
中村雄二郎のこの文は、レヴィ・ストロースを下敷きにしています。木田元はハイデッガー、鷲田清一はメルロ・ポンティーです。池上義彦はソシュールです。私たち教師がこれらに付き合うのは仕方がないことかも知れませんが、生徒にそれらと付き合うことを強いるのは得策とは言えません。高校現代文は哲学入門でもなければ、ポストモダン紹介でもないのです。しかし、そうだからといって、これらを授業で取り上げない理由にはなりません。
私の現代文の授業の目標の一つは、新聞の文化欄や雑誌の文明批評や新書本を生徒自らが読める力をつけることです。その力をつけるためにもこの種の評論は積極的に取り上げていきます。高校生のみならず世の中の活字離れが叫ばれていますが、この背景には活字に関心がないというより、書いてあることを理解できない読解力不足があるように思います。文明批評も文芸時評も、その手の新書本さえ理解できないのですから、読もうとするわけはありません。その結果、自分たちの周囲で何が起こっているかわからなくなり、論理を放棄して、わかりやすいドラマやコミックに流れ、オカルトなどの神秘主義に走ったりするのです。
哲学や、批評・評論などの思想の世界は、個別化・複雑化していますが、それに反して、生徒と生徒を取り巻く状況は幼稚化しているのですから、教師はこれらの評論文をいかにすれば生徒が自分の実感として読み解くことができるのかということを考え、生徒自らの目で自分のことや周囲を見渡すことができるのかということに工夫を凝らす必要があるのです。そのためには、それらを生徒の目線に合わせる工夫、実感に合わせる仕掛けがいるのです。それらを噛み砕き、整理して、生徒の腑に落ちる工夫をする必要があるのです。繰り返しますが、こういう作業では、本文に線を引いておしまいというわけには決していかないのです。
話を『好奇心 知的情熱としての』(中村雄二郎)に戻します。
ここで中村は、芭蕉の旅を取り上げ、旅は日常性の向こうにある非日常への飛翔、日常生活の惰性から自己を解放するものとして、そこに「好奇心」を見て取ります。
(好奇心は)なにかおもしろいことはないかと知らなくてもいいことまでむやみに穿鑿する心、あるいはもの好きといったような意味に解されている。けれども好奇心とは、私たち人間の知的活動の根源をなす情熱、つまり知的情熱にほかならない。
つまり、新鮮な気持ちでものごとに出会いたいという情熱=「好奇心」こそが人を旅に駆り立てるというのです。そして、その「好奇心」とは「知的情熱」であり、世界や自然に向ける強い関心だとし、レヴィ・ストロースを例に出して、「好奇心とは、新鮮な気持ちでものごとに出会っておどろきを感じる心であり、知ることへの情熱である。」として、文化や学問の原動力をここに求めているのです。つまり、この「知ることへの情熱」こそが「技術の正体」なのです。筆者(木田元)は次のようなギリシアの詩をあげています。
不思議なものは数あるうちに
人間以上の不思議はない、
波白ぐ海原さえ、吹き荒れる南風(はえ)をしのいで
渡ってゆくもの、四辺(あたり)にとどろく
高いうねりも乗り越えて。
神々のうち わけても畏(かしこ)い、朽ちもせず
撓(たゆ)みを知らぬ大地まで 攻め悩まして、
来る年ごとに、鋤き返しては、
馬のやからで 耕しつける(〈コロスの歌〉ソフォクレス/呉茂一訳
「アンティゴネ」『ギリシア悲劇II』ちくま文庫)
海の向こうに渡ろうとして船を造り出し、ひいては空を飛ぶために飛行機を作るのも、必要があるというより、そこには未知なるものへの情熱・好奇心がまずあり、それが技術を生み出したのです。これこそが「技術の正体」なのでしょう。つまり、先述した自然や世界を明らかにしたい、そして自分とつながったものにしたいという感情・情熱ということになります。
また、『技術の正体』では、やはり同じ教科書に掲載されている坂口安吾の『ラムネ氏のこと』にも補助線を引きました。何度も言及することになり恐縮ですが、評論文は論理を実感できてこそ初めて読解できたということですから、その実感を得させるためには、可能な限りの目配りが必要なのです。小説はもちろん、新聞も読まない生徒に、いかに教科書を有効に使うかが教師に課せられているのです。
『ラムネ氏のこと』では、「フグ」が食材として確立した経過についてこう述べています。
まったくもって我々の周囲にあるものは、大概、天然自然のままにあるものではないのだ。だれかしら、今あるごとく置いた人、発明した人があったのである。我々は事もなくフグ料理に酔いしれているが、あれが料理として通用するに至るまでの暗黒時代を想像すれば、そこにも一編の大ドラマがある。幾十百の斯道の殉教者が血に血をついだ作品なのである。
フグを食材として確立させたその背景には、フグを食べずにいられない人々、フグを食材にしたいという人々の情熱・好奇心があるというわけです。ビー玉をふたにしたラムネ瓶を発明したラムネ氏(?)や、「愛」に邪悪しかなかった勧善懲悪の時代に「愛」に徹した戯作者もまた世間の常識に背を向けた「滑稽な」人間ですが、かれらのその一見滑稽に見えるこだわり、それに徹する情熱こそが物のありかたを変えてきたのです。「技術の正体」は、ラムネ氏でもあるといえるのです。
また、『好奇心 知的情熱としての』では、知的情熱としての好奇心にあたる日本語の古語に〈すき〉(好き、数寄)をあて、その危険性を指摘しています。
日本語の〈すき〉は第一には、気に入ったものに向かって、ひたすら心が走る、いちずになる、熱中するという意味があるが、実はその裏にいわば紙一重のものとして、「歯どめがきかなくなって不幸な運命を招く」(数奇な運命)という意味があり、さらに「自由にしたい放題のことをする」(好きにします)という意味もある。
これこそが、木田氏が畏れた「技術の正体」そのものなのです。木田氏は、知的情熱によって一人歩きし始めた科学技術が暴走することに警鐘を鳴らしているのですね。近代的な理性では、人間の本性としての感情(情熱)や、好奇心に根ざす技術は制御できないのですから。
次に、暴走し始めた科学技術を実感するために、もう一本、補助線を引いてみました。の『死の再定義』という評論です。
| 前のページへ | 1/2/3/4/5 | 次のページへ |
| ● 「技術の正体」の指導案をダウンロード | 一太郎版 |